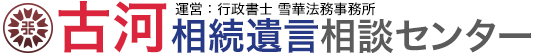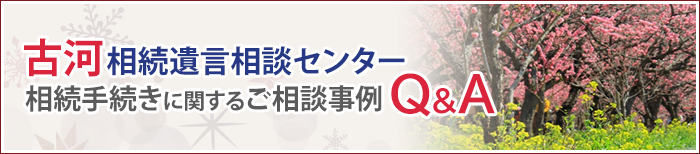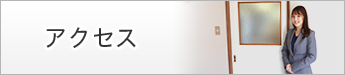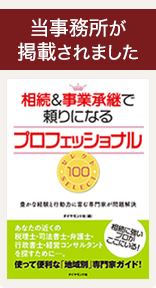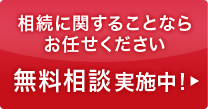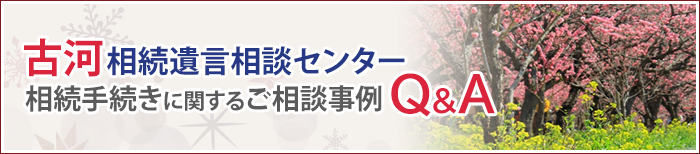
相続手続き
2025年09月02日
Q:兄が亡くなり、相続手続きをする上で必要な戸籍について行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)
古河に住む兄が亡くなりました。兄は結婚しておらず、子供もおりません。私たちの両親は他界しているため相続人になるのは弟の私のみとなります。
相続手続きについて調べたところ、まずは戸籍の収集が必要とのことでした。親子間の相続であれば、戸籍の収集はそれほど手間がかからないようですが、今回は兄弟間の相続になるため、戸籍の収集が大変とありました。具体的にどのような戸籍が必要でどのように取り寄せればよいのでしょうか。(古河)
A:兄弟間の相続で必要な戸籍についてご説明いたします。
まず、相続手続きで必要になる基本的な戸籍は下記になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
さらに兄弟間の相続では下記の戸籍も必要です。
- 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
上記の戸籍をすべて収集することで法定相続人が誰になるのか第三者に証明することができます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍では、被相続人の配偶者や子供がいるかの記載がされています。
兄弟間の相続で必要になる両親それぞれの出生から死亡までの戸籍では、両親が亡くなっていることや、被相続人の兄弟姉妹について記載がされています。
万が一被相続人の戸籍を全て集めた結果、被相続人に認知している子どもや養子がいることが分かった場合には、その人が相続人になりますので、ご相談者様は相続人ではありません。
なお、過去に複数回転籍しているケースがほとんどですので、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍収集は手間がかかります。被相続人の最後の戸籍から従前戸籍に関する情報を読み取り、順に出生時まで遡っていきます(兄弟相続の場合には、ご自身のご両親の戸籍から順に追っていきます)。すべての戸籍収集をするには、過去に戸籍が置かれていた市区町村窓口全てに戸籍請求する必要があるため、兄弟間の戸籍収集は時間がかかってしまうのです。手間と時間を要する作業となりますので、早めに戸籍収集に着手するようにしましょう。
このように、兄弟の相続手続きは戸籍の収集から手間がかかります。そのほかの相続手続きもありますので、ご自身での手続きが困難な方は専門家に依頼することもできます。
古河で相続手続きの専門家へのご相談を希望される方は古河相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。古河相続遺言相談センターでは相続の専門家が初回完全無料でご相談をお伺いいたします。まずはお気軽に古河相続遺言相談センターにお問い合わせください。
2025年08月04日
Q:父の遺産相続をするうえで揉めるような財産はなく相続人も家族のみのため遺産分割協議書を作成するほどではないと思うのですが作成するべきなのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(古河)
古河に住む主婦です。古河で遺産相続の専門家を探しておりこちらにたどり着きました。
先日、父が亡くなりました。父は長期入院しており、医者からも長くはないことを告げられていたため、私たちもある程度は覚悟していました。入院中、父から葬儀についても聞いていたため葬儀は慌てることなく身内だけで静かに執り行うことができました。葬儀は身内のみだったこともあり、そのまま遺産相続の話合いを行いました。父の遺産は大きなものはなく、古河の自宅と預貯金が数百万円です。相続人は家族のみのため遺産分割もスムーズに決まりそうなので、遺産分割協議書を作成するほどではなさそうです。このようにスムーズに進みそうな場合でも遺産分割協議書は作成するべきなのでしょうか。(古河)
A:遺産相続の手続き以外にも、相続人全員の安心のために遺産分割協議書を作成しましょう。
まず、お父様が遺言書を遺していないか確認をしましょう。遺言書がある場合には、遺言書の内容通りに遺産相続を進めるため遺産分割協議を行う必要はなく、協議書を作成する必要もありません。
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合って合意した内容を書面にしたものです。遺産分割協議書は遺産相続手続きの中に不動産の名義変更がある場合、手続きに必要になるため協議を行った際に作成することをおすすめいたします。
遺産分割協議書は遺産相続の手続きだけでなく、今後のためにも作成しておくと安心です。遺産相続は不動産や預貯金など一度に大きな財産が手に入ることになりますので、どんなに仲の良い家族であっても揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。今後のトラブル回避のために相続人全員が合意した内容を確認できるように、きちんと書面に残しておいた方が安心です。
【遺産分割協議書が必要な場面(遺言書が無い場合の遺産相続)】
- 不動産の相続登記
- 相続税申告
- 金融機関の預金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がない場合、各金融機関の所定用紙ごとに相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブルを防ぐため
遺産相続は心身ともに疲弊している中、不慣れな手続きを進めなければなりません。相続人の調査や財産調査、遺産分割協議など相続人に多くの負担がかかります。相続はそのご家庭ごとに手続きも異なり、予想以上に時間がかかってしまうケースもあります。古河で遺産相続でお困りの方は古河相続遺言相談センターの相続の専門家にご相談ください。まずは初回の無料相談をお気軽にご利用ください。古河の皆様の遺産相続を親身にサポートいたします。
2025年07月02日
Q:法定相続分の割合について行政書士の方に伺います。(古河)
ここ数週間、古河の父の容態が安定しないため、家族も覚悟するようになりました。父は80代ですし、持病もあるため、むしろここまで長生きしてくれて感謝しています。不謹慎かもしれませんが、最近は自分なりに父が亡くなった後のことを調べています。亡くなった後に慌てるよりはいいと思うんです。葬式については近所の斎場をピックアップして料金などを比較しています。あとは相続手続きになるかと思いますが、こちらについてはさっぱりわからないため、アドバイスをお願いします。
法定相続分についてですが、相続人になる予定の、母と私と弟のうち、弟は数年前に亡くなっていて、子どもがいます。この子どもが相続人になる場合の法定相続分の割合について教えてください(古河)
A:法定相続分についてご説明します。
民法で定められた「法定相続人」には順位があります。配偶者は必ず相続人で、法定相続分は相続順位により変わります。上位の人がいらっしゃる場合には、下位の人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合には、次の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
法定相続分の割合について、ご相談者様のケースに当てはめてご説明します。
【配偶者であるお母様】1/2
【二人のお子様】ご相談者様が1/4、弟様のお子様が1/4(複数名ならここから均等に分割)
なお、必ずしも法定相続分で相続しなければならないわけではなく、法定相続人全員で遺産分割協議を行って、分割内容を決めることもできます。
古河相続遺言相談センターでは、古河のみならず、古河周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。古河相続遺言相談センターでは古河の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、古河相続遺言相談センターでは古河の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
古河の皆様、ならびに古河で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
まずはお気軽にお電話ください
0280-33-3685
営業時間 9:00~18:00(平日・土曜)/※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

「古河相続遺言相談センター」は古河市を中心に下妻・野木町・五霞町など茨城県西エリアで相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。